「94%」
突然ですが、この数字が何を示しているか、皆さんは想像がつくでしょうか。
これは、弊社主催のイベントや私が登壇した外部イベントで、セキュリティの「Platformization(プラットフォーマイゼーション)」というトレンドに賛同すると答えてくださった方々の割合です。具体的には、アンケートにご回答いただいた397名のうち、実に375名が賛同の意を示してくださいました。
私が会場で投げかけた質問は、非常にシンプルなものです。
「セキュリティは関連する要素技術が多く、プラットフォームやスイートでまとめることを訴求するベンダーがあり、弊社もその1社です。このトレンドについて、どう思われますか?」
正直なところ、この結果には驚きを隠せませんでした。当初、私はこの数字を50%〜70%程度と予想していました。しかし、蓋を開けてみれば94%。これはもはや「トレンド」という言葉だけでは片付けられない、現場からの強いメッセージだと感じています。
なぜ、これほどまでに多くの日本のお客様が、セキュリティの統合化、Platformizationを求めているのでしょうか?この驚異的な数字の裏にある背景を、アンケートに寄せられた「生の声」と共に探っていきたいと思います。
ちなみに、本ポストではPlatformization自体については触れておりません。Platformizationについて概要を知りたい方はこちらのショート動画をどうぞ。詳細な説明については2025年10月開催のIGNITE 2025にてセッションがありますので、後日そちらのオンデマンド版を追記します。
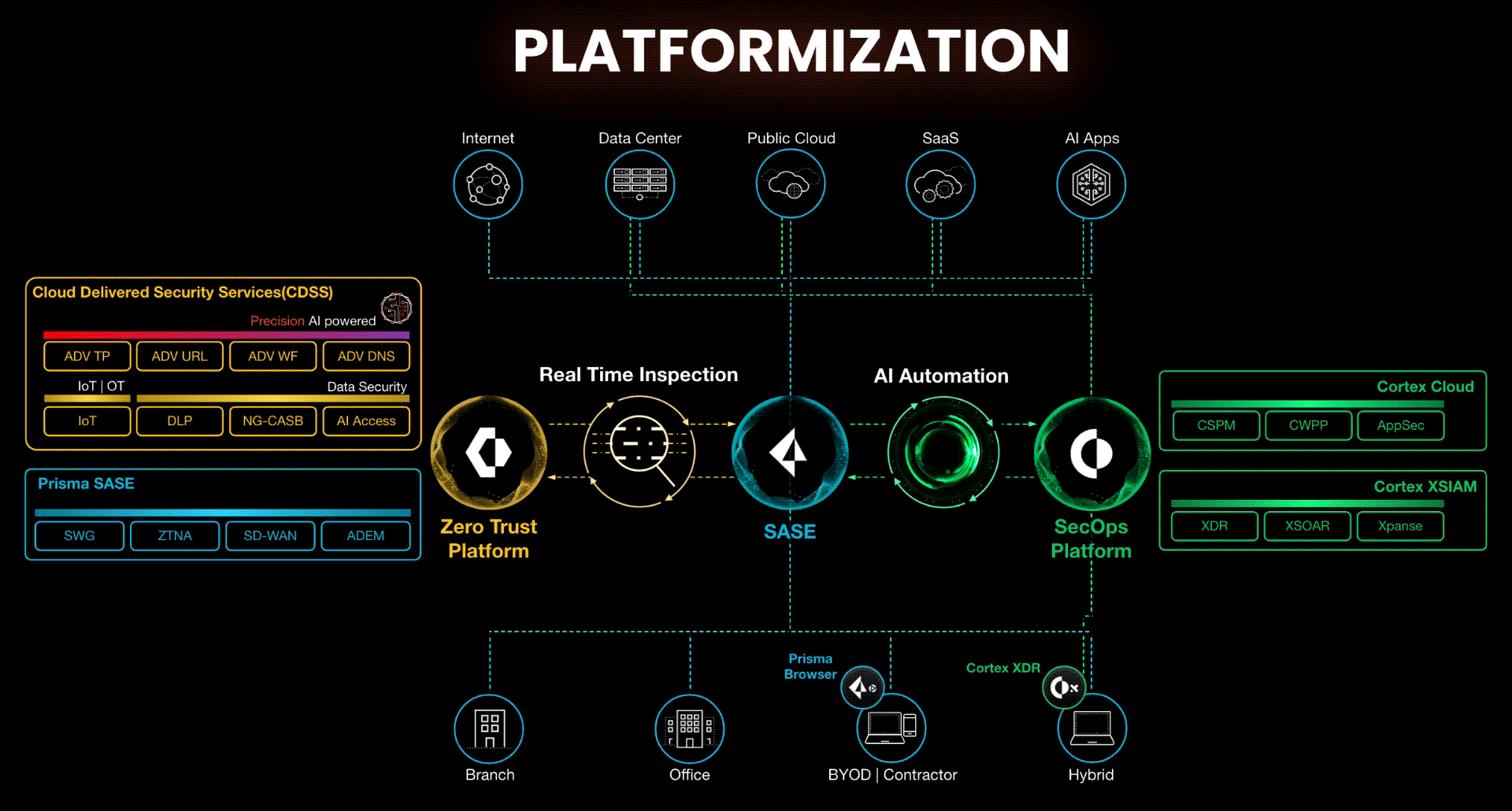
図. 日本市場向けPlatformizationの概念図(著者作成)
Platformizationが支持された、4つの理由
アンケートに寄せられた多数のコメントを分析すると、94%という数字の背景にある、4つの明確な理由が浮かび上がってきました。それは、日本市場が直面する課題そのものであり、セキュリティの未来に不可欠な要素でした。
1.圧倒的な「運用負荷の軽減」と「シンプル化」への渇望
最も多くの声が集中したのが、このテーマでした。日々増え続けるセキュリティツール、異なる管理画面、鳴り止まないアラート。多くの担当者が、本来向き合うべき脅威の分析や対策ではなく、ツールの管理そのものに忙殺されている現実がそこにはありました。
「シンプル化することで運用が楽になりそうだから。」
「つぎはぎだらけの環境だと必ず穴ができるから」
「管理が別れる分管理者の技術習得や引き継ぎが難しくなる」
特に、複数のツールが連携なくバラバラに稼働している環境の弊害は深刻です。あるユーザーからは、こんな悲痛な声も寄せられました。
「弊社はツールやSOCがバラバラで、運用工数の拡大、インシデント対応時間の短縮が困難、そして運用する技術者の確保も困難な状況である。」
Platformizationは、この複雑性の迷宮からの脱出口です。「楽になる」「分かりやすい」というシンプルな言葉の裏には、担当者が本来の専門性を発揮できる環境を取り戻したい、という切実な願いが込められています。
2.「コスト削減」への強い期待(人・モノ・カネ)
運用負荷の軽減は、そのまま「コスト」という経営指標に直結します。ここで言うコストとは、単なるライセンス費用だけではありません。担当者の人件費、新しいツールを学ぶための学習コスト、そして見えないところで膨らんでいく管理コストなど、多岐にわたります。
「全てを一体化で管理できれば、コストも業務も削減が可能と考える」
「学習コストが抑えられる」
「管理面だけでなくコストの面でもベンダーが分散している現状より良さそうにも見える」
「単一ベンダーであれば、習得までの時間も短縮できる」
個別最適で導入されたツール群が、結果として重複投資を生んでしまうケースも少なくありません。Platformという形で投資を最適化し、人的リソースをより付加価値の高い業務へシフトさせる。これは、セキュリティ部門が経営に貢献するための、極めて合理的な戦略と言えるでしょう。
3.本質的な「セキュリティレベルの向上」
運用やコストの効率化は重要ですが、それ以上にPlatformizationが支持される本質的な理由は、「セキュリティレベルそのものの向上」にあります。製品がサイロ化(分断)された環境では、インシデントの全体像を把握することが極めて困難です。
「全体を俯瞰してみることが可能なため」
「製品をまとめて統一したほうが製品同士のシナジーが高い」
「アナリストとしては調査がしやすくなるため」
「統合化し連携することでしか今後のゼロデイ対応は時間的にもリソース的にも実現できないと思う」
弊社Unit42のレポート「Global Incident Response Report 2025」は、46%のインシデントは特定に4つ以上のデータソースからの相関が必要、75%のケースでログに証拠があったがサイロ化されていて検知できなかった、と述べています。
人間であれば、身体のすべての箇所の感覚が共有されていて、頭、胸、腰など、いろいろな場所での異変を総合的に判断して、病院にいく、といった判断が可能になりますが、現状はネットワーク、エンドポイント、クラウド、SaaS、AIといった形でデータが分断されている事が多く、結果としてインシデント検知に支障をきたしています。
様々なソースから生まれる無数のデータを1つのポイントに集約するPlatformizationなら、これらの相関分析は瞬時に行われ、インシデントの検知と対応の精度と速度を飛躍的に高めることができるのです。
4.未来を見据えた「自動化」と「インシデント対応の迅速化」
AIの活用など、攻撃者の使う手口はかつてないスピードで高度化・自動化されています。これに人手だけで対抗するのは、もはや不可能です。先述のレポートでも、インシデントの5件に1件は、1時間以内にデータが流出している、4年間で3倍に加速している、とあり、数時間単位のせめぎ合いが求められる領域に突入していることを示しています。これからのセキュリティ運用は「自動化」が前提であり、そのためにはPlatformという土台が不可欠である、という先進的な意見も多く見られました。
「AIを利用し高速化した攻撃に対応するために必要だと感じたため」
「統合と自動化なしには内部不正や攻撃者のスピードに対応できないのは明らか」
「システムを統合かつシンプルに構成し、自動化も積極的に推進さることで、運用負荷を下げ、少ない人数でも取り組むべきインシデントに注力できる環境に変えていきたい」
データが統合され、一元的に管理されているからこそ、SOAR(Security Orchestration Automation and Response)のような自動化技術が真価を発揮します。プラットフォーム化は、未来の脅威に対抗するための「必然」と言えるでしょう。ネットワークやSASE領域の運用、例えば多くの方が悩まれているホワイトリスト管理なども、Platformizationだからこそ実現できるシンプルな自動化の好例です。
Platformizationは「ベンダーロックイン」なのか?
もちろん、Platformizationにはネガティブな意見もありました。特定のベンダーに依存することへの懸念、いわゆる「ベンダーロックイン」を指摘する声も、少数ながら存在しました。
「管理面でユーザーエクスペリエンスが良くなるが、ベンダー依存が進むと感じる」
「競争が働かず質の低下や価格が釣り上げられることが起こるから」
これらのご意見は、非常に的確で重要な指摘です。Platformizationを検討する上で、避けては通れないテーマです。しかし、そのリスクを認識した上で、それでもなおPlatformizationを選ぶべきだという、力強い意見があったことも、ここでお伝えしなければなりません。
「ロックイン覚悟で今後も長く続く企業にベットし、運用を効率化した方が結果的にセキュリティレベルの維持につながると思っている」
これは、もはや「どちらの製品が良いか」という議論ではなく、「どのパートナーと未来のセキュリティを共に創っていくか」という、より高い次元での意思決定が始まっていることを示唆しています。マルチベンダーの自由度を維持するコストと、信頼できるパートナーと深く連携して効率とセキュリティレベルを最大化するメリット。その天秤が、今大きく後者へと傾いているのです。
94%はトレンドか、必然か
今回明らかになった94%という数字。これは、単に「流行っているから」という表面的な理由で生まれたものではありません。
- 限界に達した運用負荷
- 最適化が求められるコスト
- サイロ化が招くセキュリティリスク
- 攻撃スピードに対抗するための自動化
これら日本のセキュリティ現場が抱える、構造的で根深い課題。それらを解決するための合理的な道筋として「Platformization」が求められている、という現実の表れです。
もはや、これは単なる「トレンド」ではなく、時代の必然といえるのかもしれません。私たちは、この94%という声に真摯に耳を傾け、お客様が直面する課題を解決するパートナーとして、セキュリティの未来を共に築いていきたいと強く願っています。